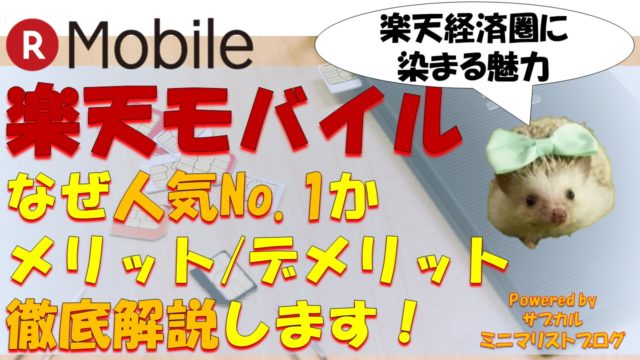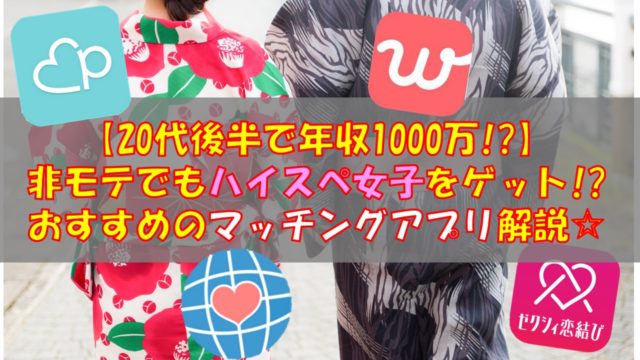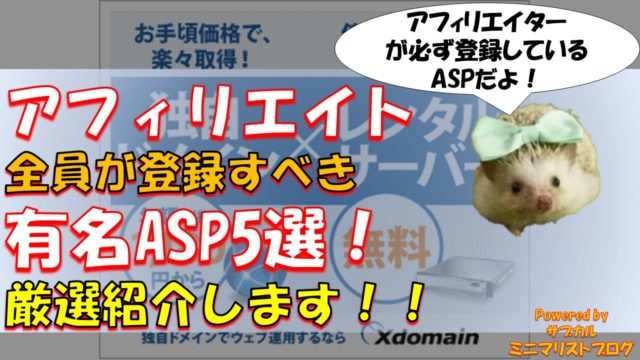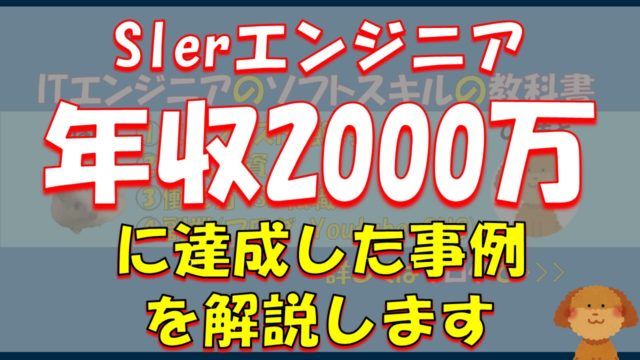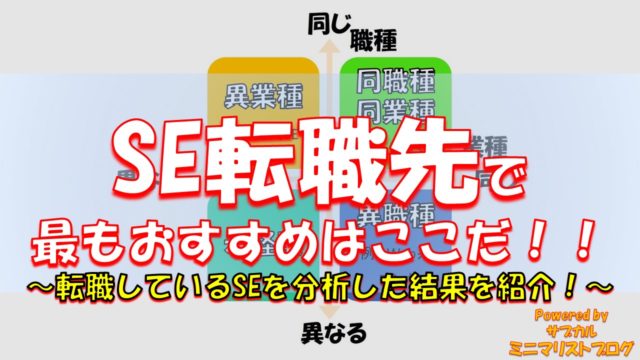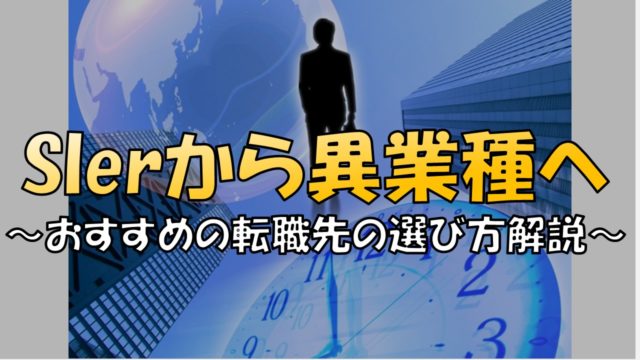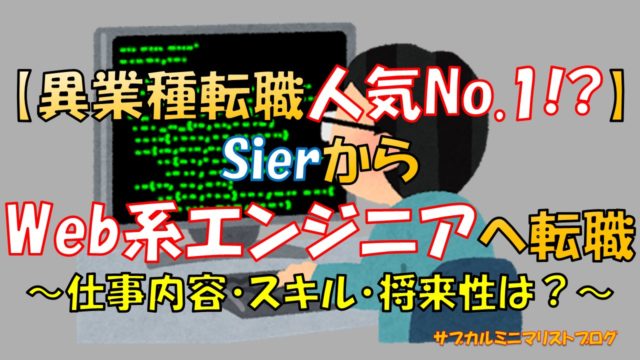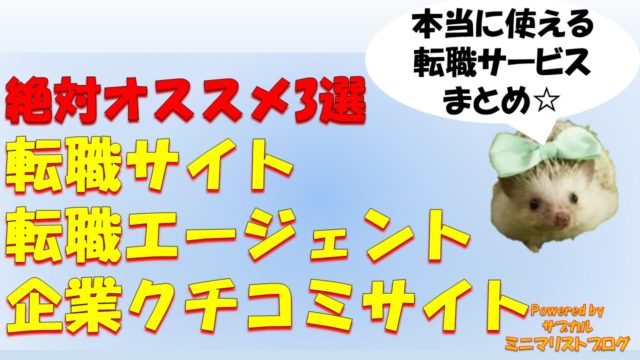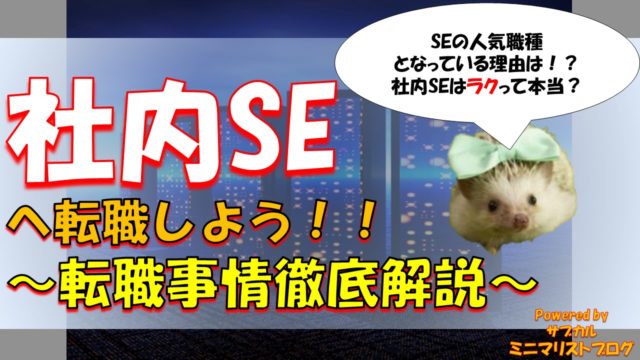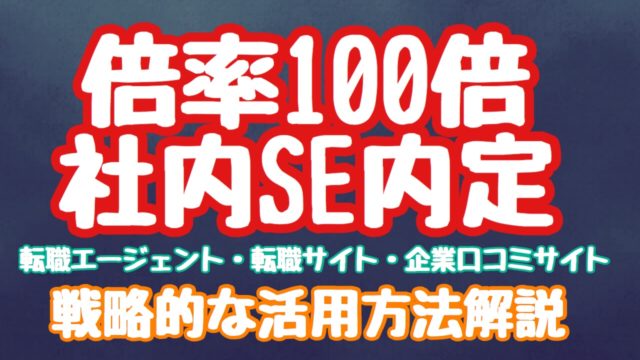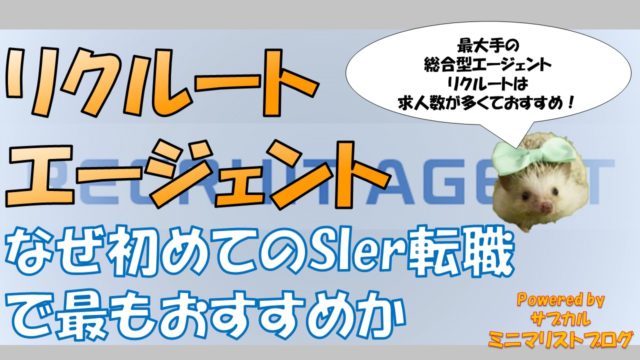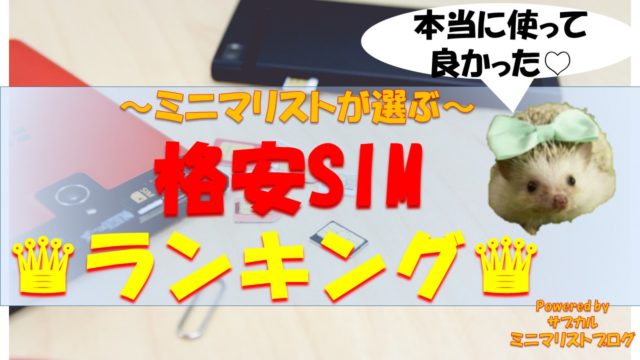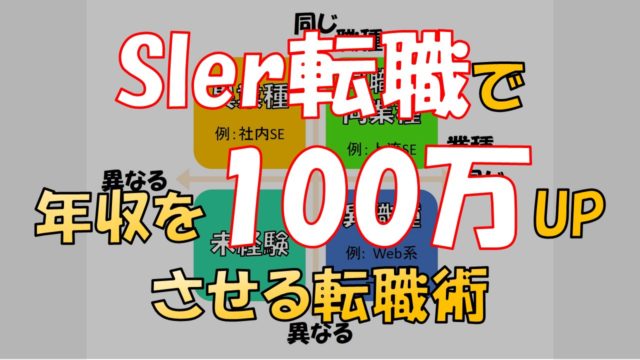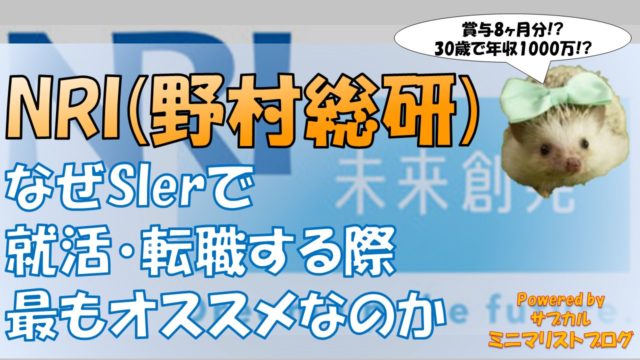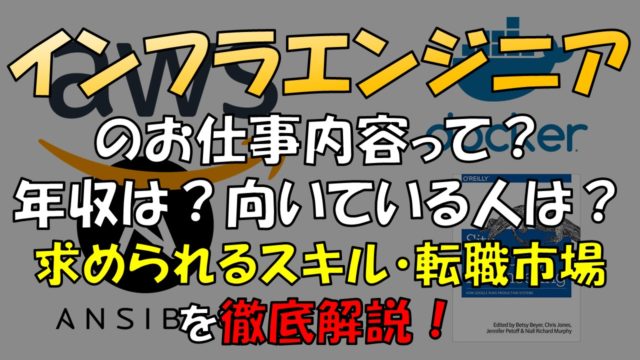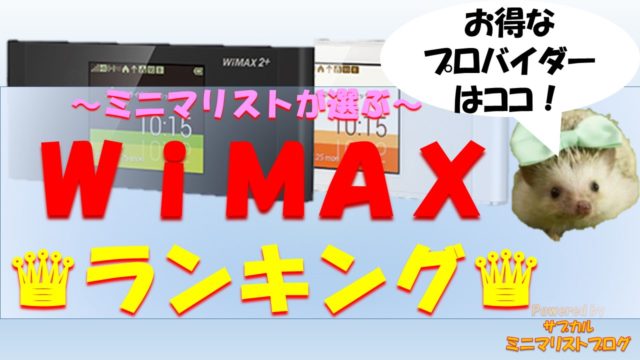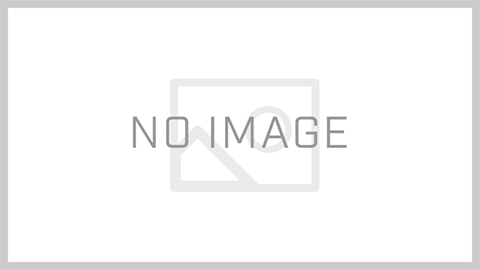今日は、デジタルビジネスによるSI企業の将来性について分析していきたいと思います。
転職活動前に準備すべき本
目次
なぜSI事業は低迷したのか~業界の変遷~

今回はデジタルビジネスを分析する上で経済産業省の資料をもとに分析していきます。
上記の図を見ると、ソフトウェア製品としての箱物を売ることから、製品を組み合わせてシステム化しサービスとして売ろうと変化していきましたが、
人月換算によるサービス提供による技術力の軽視→多重下請け構造化→業界の疲弊(労働集約型による長時間残業、賃金などの待遇悪化)と進んでいき、魅力が低下したことがわかります。
ユーザ企業とベンダー企業とは?
それは、ユーザ企業は”システムを買う側”、ベンダー企業は”システムを売る側”という意味です。
よく言われるのは、ユーザ企業が優位であり、システムを売る側はユーザ企業の文句に答えるだけの””パシリ””、いわゆる社畜と位置づけられていることです。
多重下請け構造のビジネスモデル

SI企業は多重下請け構造を成しているとよく言われています。
上流工程に行く方が良いといわれている理由は以下です
・賃金が明らかに良い(2次下請け以降では年収700万以上が激減)
・なんの事業のために利用されるのかわからない(ユーザ企業から遠くなり、1次ベンダーの部品製造のために働くことになるため)
さらに、このシステムを売る側に対する頂点として、買う側のユーザ企業が王座に君臨しているという構図です。
NTTデータに行けばいいというわけでもないのです。
ユーザ企業はどれだけ偉いのか~ユーザ企業の社内SEに行けと言うけれど~
ユーザ企業のIT投資は、依然として保守運用ばっかりで、ITを活用したビジネスモデルの変革という事業は全然できていないことが自明です。

ここではベンダー企業を、ソフトを全く提供しない企業をSI企業、ソフトも提供する企業をベンダー企業と分類していますが、多重構造としては近いものがあるし、ソフトとサービス両方手がける企業もあるのでほぼ一緒と考えてください。
| 企業形態 | メリット | デメリット |
| ユーザー企業 | エンドユーザーに近いため、ビジネス課題を解決するために顧客視点で企画・提案するスキルが養える。 | システム構築を実践することによって得られるテクニカルスキルやマネジメントスキルを養うことが難しい。 |
| SI企業 | 開発を通して、実践的なテクニカルスキルやマネジメントスキルを養うことができる。 | ユーザー視点に立ったシステム企画に参入しずらい。二次請け以下であれば、システムの全体像を把握できないことが多い。 |
| ベンダー企業 | 常に先進的な技術を習得できる。また製品を通して幅広い技術を身につけられる。 | 製品の仕様が大前提となるため、顧客視点で最適な提案を実現するための制約が大きいことがある。 |
ユーザ企業が事業を知っているのは当然ですが、保守運用しかしてなく、ましてやベンダー側も製品をブラックボックス化してベンダーロックインという技でお互いを支え合い、社畜は守りのIT事業の保守のためにお客様常駐をしているので、一向に疲弊するだけのビジネスモデルという事実は結局変わりません。
社内SEにいってもITなんて出来ないのです。企業内の花形事業に対するお手伝いという立ち位置です。
ユー子~いわゆるユーザ系SI子会社には行くな~

そういう訳で、社内SEに行くならまだしも攻めの投資へのシフトが多少期待できても、ましてやユーザ系子会社になんていっては行けません。いわゆるコストセンター化し、さらに、子会社化するとなると自分で稼げといわれ、自分たちのシステム運用をベースに社畜化していきます。
というより、入社する上でなんでも子会社というのは怪しいと思った方が良いです。
んで、気づきますよね。
従来のベンダー企業はこの単価の低いコストセンターをまるごと受け入れることによって儲けてきたのです。
ITエンジニアへの処方箋
処方箋1:Web系はどうなの?
Web企業は自社でサービスを提供しているので先駆的存在で技術力も身につく場所ではありますが、SI企業で数年経験した後では身につく業界知識も異なります。また疲弊による凡人化となってしまっていたらやりがいのために転職ももはや不可能です。
またほとんどの企業では資本力がなく、サービス残業も求められ、簡単に生き残れるほど甘くはありません。
処方箋2:共創へとすすむベンダー企業はどうなるか
このような人材にはITの素養が必要と考えられるが、そのような素養を持つ人が日本では偏って存在している。「米国ではIT従事者数のうち7割がユーザー企業に所属するが、日本ではわずか25%に過ぎず、大部分はITベンダー側にいる、という調査がある。そのため、デジタルイノベーターの育成は(ベンダーである)我々の責務と考えている」
こう言いますが、攻めの投資が儲からなければ結局コストセンターの請負というモデルからは変わりません。どうなるかは自分たちで考えるしかないのです。
処方箋3:内製化
このように、既存のSIは崩壊し、お互いの境界はなくなっていくと思われますが、
問題は、その先にぼくらはどこに行けば良いの?という選択です。
リクルートのこの記事は3年前です。こういったブームに乗っている企業もありますが、これからという企業ももちろんあります。
つまり、ぼくらが今後行く場所は、
これから内製化や共創を想定しIT投資をしようとしている、ユーザ企業などが挙げられます。
新規事業であれば、古くからいる居座りおじさんからの弊害のリスクを減らせるかもしれません。
転職活動前に準備すべき本
まとめ
SI事業は今後縮小し、魅力も低下しているビジネスであるということがわかりました。
問題はこのあと自分はどこに行くかということです。
スキルがミスマッチする前に見極めないといけません。
また、面白くない仕事に従事し続ける自分から脱却しなければいけません。
エンジニアの転職希望者の7割が転職を希望すると言われる社内SE。。。
何も実力もないぴなもとが、倍率100倍の超難関有名ホワイト企業に内定を獲得し、転職を決めた方法、知りたくないですか?
社内SEへの転職は非常にテクニック的な要素が強く、内定をうまく獲得できなければ、
高倍率の沼にハマり、転職活動が長期化してしまうリスクも大きいです。
また、会社により様々な社風がある事業会社を受けるのですから、安易に社内SEに行けばホワイトとも言えないのが危険なところであり、
そんなぴなもとが、倍率100倍の競合から勝ち取った戦略的テクニックを以下で解説していています。是非一度手に取ってみてください。